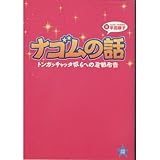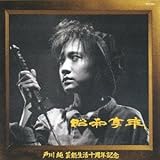サブカルってなんだっけ
ζ*’ワ’)ζ<日記だよー。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ちょっとテンションあがって、ナゴムレーベルの曲を聞いていました。
(ちょっとじゃなく、割りと定期的に発作が起きます)
ナゴムの話すると長くなるので一旦置いといて。
あ、「ナゴムの話」は超オススメです。
で、当時からナゴムとかは「サブカル」枠だろうと漠然と思っていました。
でも「サブカル」って言葉すっげー曖昧。というかなんだかわからないですよね。
コアマガ派とマガジンハウス派とか、話は知っていてもようわからない。
例えばヴィレヴァンから「サブカル本は一掃された」なんて話があったけども。
でもどこからどこを線引いてサブカルなのか。
サブカル者は昔から「ヴィレヴァンはサブカルじゃない」みたいに言ってることもあったし。どっちなんだか。
あ、ヴィレヴァンのフリーペーパーデビューしました。見てね。
特にぼくが「ええっ?」って思ったのが、「アニメはサブカルじゃない!」という話。
オタクVSサブカル論争なんかもあったし、ある程度理解はできている。けれども実際そう聞くと不思議な感じ。
というのも、ぼくが中高時代に悶々として「普通でありたくない」と願っていた時であったのが、ナゴムと、深夜やっていた「アニメだいすき!」(かな?)というOVA流す番組だったから。
どっちも「異常」なものだった。ここに近づけば解放される!って感じました。
だからアニメって、メインカルチャーじゃない気がずーっとしていて。サザエさんとかポケモンとかはともかく、今でも深夜アニメの話って人前でできないもん。サブのカルチャーじゃないの?って。
ただ、確かにサブカルと呼ばれる文化圏のものと萌えアニメが同じ箱に入ってるのは珍妙なのもわかる。
日本という箱の中だと、その2つは同じ箱で混沌としている気はするんだけどね。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHKでやっていた宮沢章夫の「ニッポン戦後サブカルチャー史」は、そういう点で面白かったです。
原宿セントラルアパートも、ニューウェーブも、おたく文化も「サブカルチャー」。
じゃあ定義はなにかっていうと、「逸脱していること」。
なるほど、いずれもメインカルチャー・ハイカルチャーから逸脱している。ジャンルはバラバラだけど。
ひっくり返すと、かつてサブカルと呼ばれたものを追い求めても、今逸脱していないなら、それはサブカルではない。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
もうちょい考えてみる。
逸脱といっても、「なぜ逸脱するのか」に差はあるから、3つにわけてみる。
わけるっていっても円と円重なってるけど。
・おたくカルチャー
アニメ・マンガ・アイドル・鉄道などなど。知識・収集・二次創作の色が強い。
今は「オタク」「OTAKU」とカタチをかえて、精神性はガラッと変わった。
・カウンターカルチャー
反骨精神や、強い軸の通った思想からなる文化。
フォーク、パンク、ニューウェーブのような音楽や、ゴスやロリィタなどのファッションやアート。
時代がかわると敵対するものが変わるので、必然的に波も変わっていく。
・サブカルチャー
その他(適当)。
なんだかよくわからないもの集め、路地裏の変な店から、アウトサイダー・アート、ドラッグ文化、るんぺんのおっちゃんの飲み屋、ヤンキー、エログロナンセンス、B級映画、風俗アダルト文化等々。
ものによってはカウンターカルチャーやおたくカルチャーにもなりうる雑多な感じ。思想があるのかないのかわからないもの。
適当に書いてるから詳しい人は自分で書いたほうがいいよ!ぼくの脳内整理ですから。違うと思う人はそれでいいと思うの。
これら全部ひっくるめて、逸脱した「サブカルチャー」だなーと思ってます。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
例えば、ぼくは戸川純がすごい好きです。
で、戸川純は多分カウンターカルチャーだったと思うのね。ニューウェーブですよ。
反骨精神まで行かなくても、自分の好きなモノを貫くぜ的なものはあったと思う。
「昭和享年」とかは反骨じゃなくて、昭和歌謡愛でしょうし。
むしろその理論でいうとビートルズのほうがよっぽどカウンターカルチャーですね。
まあ精神性はよくわかんないのでいいや。
戸川純のすごいところは、今聞いても「逸脱」しているところです。
他にないもんね。
だから、戸川純は「サブカルチャー」って言われる。
一方でかつて、カウンターカルチャーだったジャズやブルースやフォーク。
今は戦うものが貧困や差別じゃない。
当時の逸脱を聞くことは、現在からの逸脱なのかもしれない。
でも多分、サブカルチャーって言われないよなー。
今も差別を唄う三上寛とか、お母さんいい加減あなたの顔は忘れてしまいましたな遠藤ミチロウはサブカルチャーの塊だけども。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
たとえばおたく文化で、癒し系アニメ。
これって「オタク」とか「サブカル」なのか?と言われると悩ましい。少なくとも、逸脱はしてない。
なんだろうなあ、ロックと、癒やし系ロックの違いみたいな感じ。いい悪いじゃなくて、漠然と違うなーって。
ここで、最初にあげた「オタク」「サブカル」の話でハッとなる。
ようはオタクとサブカルは幅が広すぎて、重なるところと重ならないところが漠然としている。
ぼくはサブカルの中にオタク文化がまるまる入っていると思っているんだけど。ちょっとはみ出してるところもあるようだ。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
「逸脱」って、人間のはみ出してる部分のような気がします。
表現されていないものは山ほどある。
都内某所の裏路地歩いていた時。
昼間から酔っ払ったおっちゃんが、ゲロをだらだらこぼしながら道を歩いていました。
ゲロはなめくじの跡のようでした。
うわー、サブカルだーと思いました。
文化じゃねえけどもさ。これを調べて行ったら文化じゃろ。
尊敬するライターさんが、「なんでも集める」コレクターです。
本当になんでも。
なぜか。
「集めるとわかるものがあるから」。
わかるものがなければ、集めるのもやめるそうです。
すげーハッとなった。
たとえば札束の写真。どうでもいいね。
集めていくと、人間のある習性がわかるのです。
何がわかるかは内緒。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
メインカルチャー・ハイカルチャーが目指すのが、人間探求だとしたら、
サブカルチャーもまた、逆側から人間を目指す文化だなーと、その集める話を聞いて感じました。
向きが違うだけなんだよなー。
どの文化層も結局、生と性と死が入ってくるし。
もっとも、嶽本野ばらは想像へ逃避して明日への英気を養うのを「メルヘン」、現実から決別する行為を「ファンタジー」と呼びました。
あっそうか。決別も文化か。
そしてその決別した人間を研究する文化もあり……。
多分いちばん面白いのは、いろんな人間のバラバラな様子を見ることなんだろう。
あとはどう出力するか。その方法の違いでしかない。
人と異なりたいとも、同じでありたいとも思わない今。
世の中面白いことしかないです。